|ホームページのトップへ| |音楽のページのトップへ| |オーマンディ年表|
ユージン・オーマンディ&フィラデルフィアの芸術
1968年から1980年までの12年間に、RCAに残した録音から選りすぐってCD化。
(第1回1999年15タイトル、第2回2001年20タイトル、第3回2003年20タイトルの計55タイトル発売:全て初回限定盤)
![]()
<<私が購入した9タイトル>>
|
収録曲 |
|
 |
ベートーヴェン
交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」(1980.9.29) 「エグモント」序曲Op.84(1970.2.4) オーマンディ最晩年のデジタル録音による「エロイカ」。悠然たるテンポで進むスケール雄大な演奏。世界初CD化。 オーマンディ&フィラデルフィア管によるベートーヴェンの交響曲は、第1・5・7・9番がモノラルで、次に、1961〜1966年に、交響曲全集(コロムビア)を完成し、その後は、1980年(デジタル、RCA)のこの「英雄」のみである。 オーマンディは、録音回数は少ないが、演奏会ではベートーヴェンの作品を頻繁に取り上げていた。 この曲で、オーマンディが独自の改定を行っているのが、終楽章の六分過ぎ、トランペットに続く、木管の8分音符の動きを、楽譜にはないトランペットで補強している。<解説:市川幹人> このCDは、管楽器の音がベートーヴェンには少しふさわしくないと思えるようでもあるが、実に丁寧に演奏されており、好感が持てる「英雄」となっている。 |
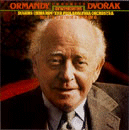 |
ドヴォルザーク
交響曲第7番ニ短調Op.70 (1976.10.19) いずれもオーマンディにとって生涯唯一の録音となったもの、LP発売以来名盤の誉れが高い名演。 じっくりと音楽の流れを練り、細部に神経を使い、やや遅めのテンポでたっぷりと歌う。特に弦楽器の音色が際立つ演奏である。 この時期、1975年にギルバート・ジョンソン(首席トランペット)、1977年にジョン・デ・ランシー(首席オーボエ)、1978年にメイソン・ジョーンズ(首席ホルン)など、オーマンディ時代とともに語り継がれる名手たちが、ステージから去っていった。<解説:市川幹人> わたしは、この曲では、ジョージ・セル指揮、クリーヴランド管弦楽団のレコードを超える演奏はないと思っていた。引き締まった筋肉質で、細部に至るまで自在に歌いながら崩れないフォルム、それでいて情感が香る演奏である。 オーマンディの演奏も、これに勝るとも劣らず、弦楽器を主体にしたフィラデウrフィア・サンドで、たっぷりと歌い上げる演奏は美しい。 |
 |
ドヴォルザーク
交響曲第9番「新世界から」(1976.5.12) スケルツオ・カプリチオーソOp66(1968.6.11) スラヴ舞曲第8番ト短調Op46-8(1971.9.28) スメタナ(1824-1884) 交響詩「モルダウ」(1970.2.5) スケールの大きな、たっぷりとした響きで表現した名演。 オーマンディは、「新世界より」を5回録音している。?年、1946年、1956年、1966年(ステレオ、コロムビア。フィラデルフィア管がストライキ中のため、ロンドン響を指揮。)、1976年(ステレオ、RCA)。<解説:市川幹人> 曲がいいのか、演奏がいいのか(どちらもいいにきまっとる)、何度聞いても飽きのこないCDである。 |
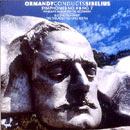 |
シベリウス
交響曲第4番イ短調Op.63(1978.3.4) シベリウスの神秘に満ちた透明な響きを堪能できる。全曲世界初CD化。<解説:市川幹人> |
|
|
ヨハネス・ブラームス(1833-1897) 1.アルト・ラプソディOp.53 [1969.9.1] リヒャルト・ワーグナー(1813-1883) グスタフ・マーラー(1860-1911) オーマンディは、SP時代にマーラーの「復活」を電気録音により初めて録音(1936年ミネアポリス響とのライヴ)した知られざるマーラー演奏のパイオニア。 数あるオーマンディとフィラデルフィアのレコーディングの中でも、間違いなく最も感動的な演奏の一つに数えられるだろう。<解説:市川幹人> |
 |
ベルリオーズ 幻想交響曲[1976年ステレオ] 交響組曲「寄港地」 ラ・マルセイエーズ ソロ・パートの呆れるほどの巧さ、弦楽セクションの美しさ。 オーマンディは「幻想」を、1950年、1960年、1976年と、通算3回録音している。 オーマンディは、第4楽章の「断頭台への行進」で、トランペットにより木管楽器と同じ音型でオクターヴ上のBフラットまで上昇するという改定を行っている。<解説:市川幹人> わたしは、「幻想」は、ミュンシュ・パリ管のLPレコードを持っている。この1枚しか持っていないし、他のはいくら聞いても心に残らなかった。私の耳にはこれが理想の「幻想」としてこびりついている。ほかの演奏を聞く必要はないくらいだ。緊迫感にあふれたテンポ、若々しい情熱と生命力、メリハリもすごい。 上記に対し、オーマンディ&フィラデルフィア管の第一印象も、「チョット違う」と言う感じだった。しかし、何度か聴くうちに、そのきらきらとした響きに吸い込まれていった。 |
| クラシカル・マーチ集
|
ビゼー:歌劇「カルメン」〜闘牛士の行進 (1972.4.25) ワーグナー:歌劇「タンホイザー」〜大行進曲(1972.6.15) シューベルト:軍隊行進曲(1972.6.15) イッポリトフ=イワーノフ:酋長の行列(組曲「コーカサスの風景」より)(1973.1.23&24) マイアベーア:歌劇「預言者」〜戴冠式行進曲(1973.1.23&24) メンデルスゾーン:劇音楽「真夏の夜の夢」〜結婚行進曲(1972.6.12) リムスキー=コルサコフ:歌劇「金鶏」〜婚礼の行列(1973.4.11&12) プロコフィエフ:歌劇「3つのオレンジへの恋」〜行進曲(1972.6.12) ベートーヴェン:劇音楽「アテネの廃墟」〜トルコ行進曲(1973.1.23&24) .ヴェルディ:歌劇「アイーダ」〜大行進曲(1972.6.12) J.シュトラウス:ラデツキー行進曲Op.228(1972.6.15) スーザ:星条旗よ永遠なれ(1973.10.10) スーザ:自由の鐘 グールド:ヤンキー・ドゥードゥル [世界初CD化] ヘンデル:歌劇「ユダス・マカベウス」〜見よ、勇者は帰る[ハリス編](1971.4.&5.) 中国民謡「サン・ペイ」(中国の労働者と農民たちの行進曲)[世界初CD化](1972) LP以来何度も再発売を繰り返してきた名盤。フィラデルフィア管弦楽団の圧倒的なブラス・セクションの輝かしい響きを堪能できるクラシック・マーチ集。<解説:市川幹人> |

|
ピョートル・イリイチ・チェイコフスキー(1840-1893) セルゲイ・プロコフィエフ(1891-1953) オーマンディが指揮者として始めて(1924年9月)指揮した曲が、このチャイコフスキーの第4番です。 この曲の録音は、1947年(モノラル、コロムビア)、1953年(モノラル、コロムビア)、1963年(ステレオ、コロムビア)、1973年(ステレオ、RCA)の計4回、録音しています。 第2楽章、冒頭の有名なオーボエのソロは、ジョン・デ・ランシー(1954〜77年首席)。彼は、名手マルセル・タビュトー(1914〜54年首席)の弟子。<解説:市川幹人> フィラデルフィア管の音は、迫力満点でありながら、決して乱暴にならない。ぴったりそろったハーモニーの美しさに、聴いて”幸せだなー”と感じる1枚です。 |
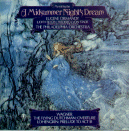
|
フェリックス・メンデルスゾーン=バルトルディ(1809-1847) 1.劇付随音楽「真夏の夜の夢」Op.21&Op.61[1976] リヒャルト・ワーグナー(1813-1883) この曲の録音は、1957年(モノラル、コロムビア)、1963年(ステレオ、コロムビア)、1976年(ステレオ、RCA)、の3回録音している。 「スケルツオ」の最後に登場する有名なフルート・ソロを演奏しているのは、マレイ・パニッツ(1961〜89年首席)である。彼は、伝説の名手、ウイリアム・キンケイド(1921〜60年首席)が引退し、その後、1シーズンおいて入団した。<解説:市川幹人> |
![]()
<<その他のタイトル>>
シベリウス
交響曲第5番変ホ長調Op.82(1975.11.118)
交響詩「伝説」Op.9(1975.12.10)、交響詩「タピオラ」Op.112(1976.10.26)
シベリウス
交響曲第1番ホ短調Op.39(1978.4.17)、「カレリア」序曲Op.10(1977.11.2)、「カレリア」組曲Op.11(1975.12.10)
マーラー
交響曲第1番ニ長調「巨人」[「花の章」付き](1969.5.21) [世界初CD化]
R.シュトラウス
メタモルフォーゼン(1978.2.8) [日本初CD化]
チェイコフスキー(1840-1893)
マンフレッド交響曲 [1976.10.27]・・・カットなしの全曲盤。
ピョートル・イリイチ・チェイコフスキー(1840-1893)
1.交響曲第1番ト短調Op.13「冬の日の幻想」 [1976.10.11]
2.交響曲第2番ハ短調Op.17[小ロシア] [1976.1.7]
3.交響曲第3番ニ長調Op.29「ポーランド」 [1974.10.28&29]
レインホルド・グリエール(1875-1956)
交響曲第3番ロ短調Op.42「イリア・ムーロメッツ」 [1971.10.6]
セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)
3つのロシアの歌Op.41[1973.3.24]
セルゲイ・プロコフィエフ(1891-1953)
カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」Op.78 [1974.10.24&1975.2.26]
セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)
合唱交響曲「鐘」Op.35 [1973.3.24]
セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)
1.ピアノ協奏曲第3番ニ短調Op.30 [1975.2.12]・・・オーマンディとアシュケナージとの唯一の共演。
中央楽団集団創作
2.ピアノ協奏曲「黄河」 [1973.10.10]
リヒャルト・シュトラウス(1864-1949)
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 [1975.2.26]、2.交響詩「ドン・キホーテ」 [1972.1.19]
ドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906-1975)
交響曲第13番変ロ短調Op.113「バービイ・ヤール」 [1970.1.21&23]
ドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906-1975)
交響曲第14番ト短調Op.135「死者の歌」 [1971.1.4&6]、2.歌劇「ピータ・グライムズ」より [1976.9.26]
ドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906-1975)
1.交響曲第15番イ長調Op.141 [1972.10.4&5]
ベラ・バルトーク(1881-1945)
2.4つの管弦楽曲Op.12、Sz.51 [1969.11.10]
メンデルスゾーン
交響曲第3番イ短調Op.56「スコットランド」(1977.11.2)
序曲「フィンガルの洞窟」Op.26(1979.4.21)
「真夏の夜の夢」Op.61より(1976.4&5.)
他
![]()
最終更新日:2004/7/15
|ホームページのトップへ| |音楽のページのトップへ| |オーマンディ年表|